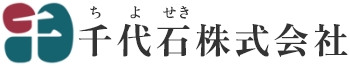横浜市金沢区、豊かな自然に包まれた地福山に佇む宝珠院
真言宗御室派の末寺として、また東国八十八ヵ所霊場第72番札所として、
長きにわたり人々の信仰を集めてきました。
その起源は天文年間(1532~1555年)に遡り、隆成法印により開山。
江戸時代の寛永年間(1624~1644年)には、地頭・豊嶋刑部少輔信満が大檀那となり、
堂宇の整備が進められました。
◆ 祈りの中心、本尊大日如来
本堂に安置されるご本尊・大日如来像は、宝珠院の信仰の核心を担っています。
大日如来は宇宙の真理そのものを象徴する仏であり、真言宗において最も重要な存在の一つ。
そのお姿は、訪れる人々に力強くも穏やかな安心感をもたらし、心の拠り所となっています。
もともと本尊として祀られていたのは、死後の世界を見守る慈悲深き地蔵菩薩像。
その手に持つ「宝珠」が「宝珠院」の名の由来とされ、
今も境内の入口や堂内にて静かに人々を見守り続けています。
時の流れとともに本尊は大日如来へと変わり、
祈りの場としての意味がいっそう深められてきました。
◆ 寺宝と仏像の息づき
宝珠院には、時代を超えて受け継がれてきた数々の仏像や寺宝が大切に守られています。
中でも、江戸時代の仏師・三橋薩摩による弘法大師像は、当時の精緻な技術が光る逸品です。
その後、子孫である三橋永助の手により修復され、今も変わらぬ姿で祀られています。
また、千手観音菩薩坐像や秘仏の聖天像・弁才天像も境内に安置され、
仏教の教えと人々の祈りを今に伝えています。
◆ 自然と静けさの中に宿る安らぎ
宝珠院のもう一つの魅力は、自然が織りなす景色にあります。
境内の中央にそびえる大イチョウは、横浜市の名木にも指定されており、
春には芽吹き、秋には黄金色に染まる姿で訪れる人々の目と心を楽しませてくれます。
参道脇に佇む五重石塔は、精緻な装飾とともに寺の静けさを引き立てる存在。
その近くには、愛らしいフクロウの置物たちがひっそりと寄り添い、
「不苦労(ふくろう)」の願いを込めて参拝者を見守っています。
その姿は、思わずほほえみがこぼれる、心和む風景のひとつです。
風のそよぎや鳥のさえずり、時には犬の鳴き声も重なり合い、
自然とともにあるこの場所ならではの穏やかな時間が、静かに流れていきます。



宝珠院は、歴史とともに紡がれてきた祈りの場であり、
今もなお、多くの人の心に寄り添い続けています。
【山号】地福山
【寺号】宝生寺
【院号】宝珠院
【宗派】真言宗御室派