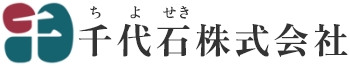今日は7月7日、七夕ですね。
七夕(たなばた)は、
古くから行われている
日本のお祭り行事です。
その起源は…
- ①棚機(たなばた)という
- 織り機で着物を織り、
- 秋の豊作を願い神さまに
- お供えした日本古来の神事
- ②おりひめ
- (琴座のベガ・裁縫の仕事の星)
- と、ひこぼし(鷲(わし)座の
- アルタイル・農業の仕事の星)の伝説
- ③奈良時代に中国から伝来した
- 乞巧奠(きこうでん)という
- 裁縫、芸事や書道の上達を願う行事
- 長い歴史の中、仏教の伝来と共に
- この3つが合わさって
- 七夕はお盆の準備として
- 7月7日に行われるようになりました。
- (お盆の時期は7月と8月の地域があります)
牽牛星は彦星(ひこぼし)、織女星は織姫星(おりひめぼし)と呼ばれ、ベガとアルタイルは夏の星空を彩る代表的な「夏の大三角」を形づくる星です。二つの星の間には、七夕伝説と同様に天の川が流れています。ベガ(織姫)とアルタイル(彦星)は日が沈む頃にはすでに東の空に現れており、深夜には南の空高くに昇ります。
- 今日、見られるといいですね。


お盆にはお墓参りに行きましょう。